**********
いつものことながら、「世に出る人は違うわぁ~」と思いながら読みました。
こう書いてしまうとおおよその年齢がわかってしまうかもしれませんが、学校教育において、渋沢栄一を歴史上の重要人物としては習わなかった気がします。
NHKの大河ドラマで取り上げられたり、一万円札の肖像に採用されたり、近年の渋沢栄一さんの活躍には目を見張るものがあります。
ということで、前々から気になっていた本書を読み始めてみました。
「論語と算盤」という本を渋沢栄一本人が著したわけではなく、渋沢栄一の講演をまとめたものです。
10章に分かれていますが、全体を通して、彼の人生論や経営哲学を学ぶことができる本となっていました。
関係のないくらい遠いものと思われていた、孔子の教えの「論語」と経済活動=「算盤」を調和させて国家を繁栄させていこうという気概から、もう非凡さを感じます。
渋沢本人は自分自身について、「四回ばかり変化しています」と語ったそうです。「尊王攘夷」「文明開化」「明治維新」「殖産興業」という時代の大きな潮流にそのまま棹さしている「時代の児」と評されていたとか。
自分の信念を持ちつつも、時代の流れを読んで素早く判断し、必要とあらば方向転換する。そんな非常に難しいことをやってのける能力があったのだなと思いました。そして何よりエネルギッシュ。そうでなければ何百という組織の設立に関わったり、70歳を過ぎて渡米したり、80歳をすぎて子をなしたりできません。と、ここまで渋沢の人生をかいつまんで書いてみましたが、本書の本筋はそこではなく、先述したように、人生論や経営哲学について行った講義がまとめられたもので、まさしく渋沢栄一の思想なくしては日本の近代化はなされなかったのではないかと思うような大事な教えばかりでした。
個人が利益を求めずにどうやって国家が繁栄していこうか。ただし、そこに道徳がなければならない。政治の方ばかりに重きを置き、どちらかというとお金を稼ぐということに後ろめたさを感じるような時代・文化だったはずですが、的を射たことをぴしっと言っておられます。そして、「道徳」的な考え方を非常に大事にしていて、私利私欲にまみれた商売にはきちんとノーと言っています。この姿勢(自分たちの利益だけを追求する姿勢)が日本経済の発展を阻んでいると、またまたぴしっと言っておられます。
それから、この時代にはかなり最先端の考え方であったであろう、女性への教育、女性の活躍の重要性を説いておられます。素晴らしい。
はたまた、教育の質についても嘆いておられ、知識詰め込み型ではいかん、みんながみんな同じような人間になるような教育はどうしたものか、とおっしゃっています。ここは現在継続中の教育に対する問題意識と似通っていると感じた部分と、職位が低い、たとえば運転手になるような人に、将来職位が高くなるような人と同じような教育をしてもうんむんかんむん・・・というところはちょっと違和感を覚えたりしました(ただしここは私の読み方が悪かった可能性もあり)。
良心、思いやり、道徳・・・こういった言葉が何度も出てきます。経営哲学として、こういったことを大事にしていれば、あの企業のあんなニュースやこんなニュースは出てこないのになぁ、とか合法詐欺とでもいえそうなあんな商売は成り立たないのになぁとか、しみじみ思いました。
本書に書かれていることを全て実践できるようになったとしたら、それこそ聖人君主になれそうです。時代を経ても本書に書かれている多くのことは色褪せないですし、経営者のみならず、多くの人にとって参考となる本だと思います。素晴らしいことが次から次へと書かれているので、若干右から左へ受け流したところもあるので(途中寝落ちしたりもした)、折に触れて読み返して、自分を省みるきっかけの本にしたいと思いました。
**********
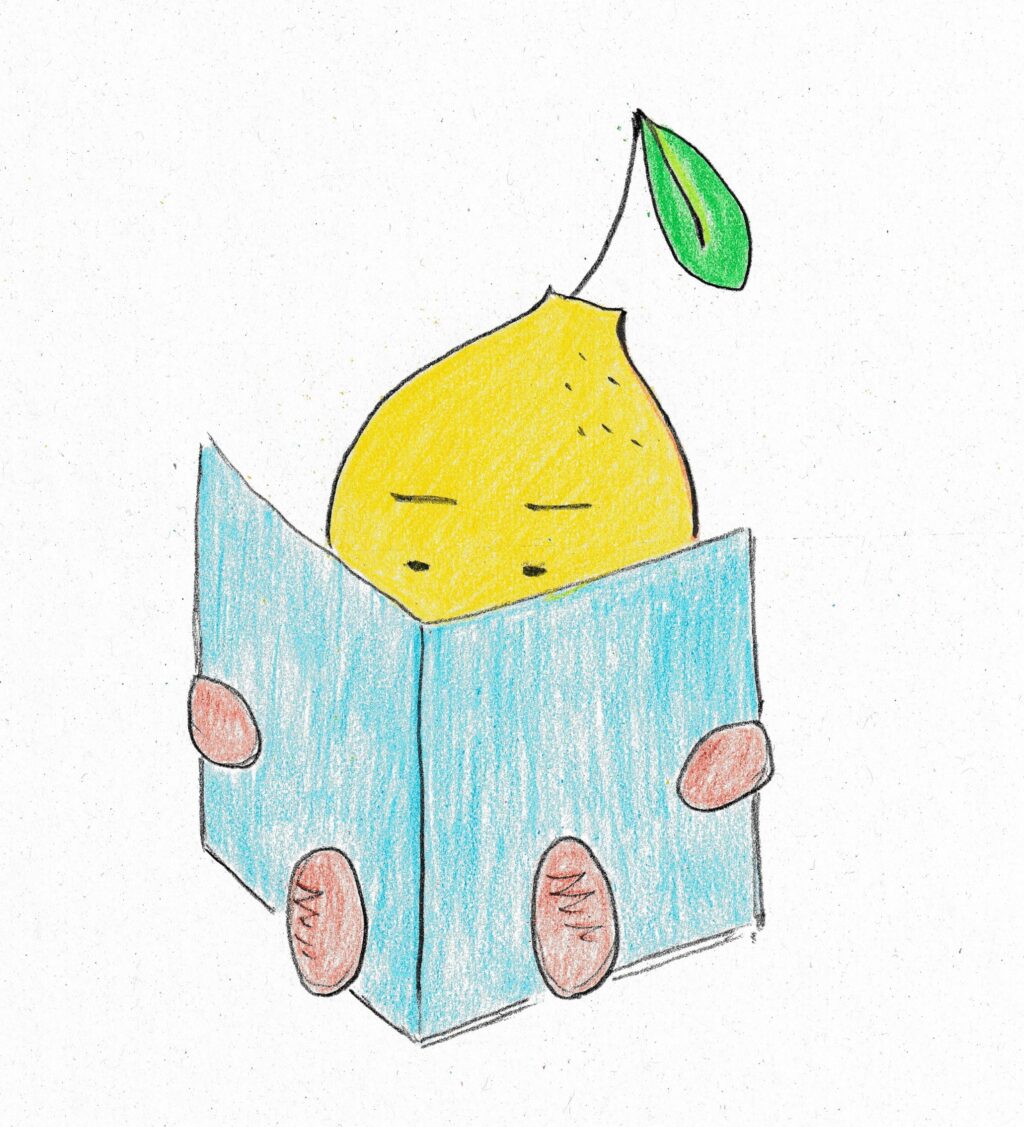
子どもたちが夏休みに入ると、やはり、というかなぜか、やたらと忙しくなります。こちらは通常勤務なんですけどね~。ということで、読了してからだいぶ経ってしまいました。
本書は、どんな人にとっても読んでみる価値がある本だと思いました。どこか刺さるところがあるはずです!
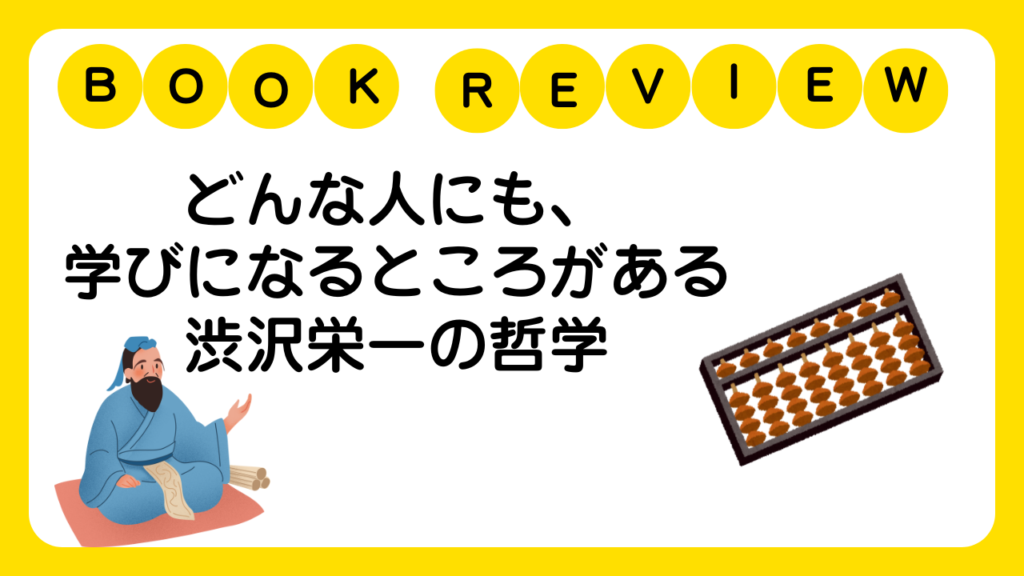


コメント