*********
久々の時代小説。慣れない言葉遣いにとまどったのもほんの一瞬。すぐに、すごい引力で物語に引き込まれました。評判通りの素晴らしい作品でした。
物語は、木挽町で二年前に起きたとある仇討ちについて、何やら関係者と思しき人物が、真相を聞きに回り、その事件を知っている者、実際に見た者たちが、その仇討ちについて語るというもの。
まず、仇討ちというものが、きちんと御国の公認で行われるものであって、仇討ちが成し遂げられない場合には、郷里に戻ることは許されないなんて、初めて知りました。この制度がないとこの物語自体が成り立たないのですが、武士の気位の高さが表れている制度だなと思いました。
仇討ちを成し遂げた菊之助を知っていて、菊之助本人やその仇討ちについて語った人物は5人で、それぞれの独白とでもいうような形式で展開されていました。彼らは、それぞれが苦労人で、出自からこれまでの来し方についても語るよううまい具合に聞き手に導かれますが、これがまた、5人それぞれの描かれ方が見事で・・・5人というのは以下のとおり。
・木戸芸者の一八
・芝居小屋立師の与三郎
・衣裳部屋のほたる
・小道具の久蔵の内儀お与根
・筋書の金治
5人が5人とも、それぞれ紆余曲折を経て、物語の舞台である木挽町の芝居小屋にたどり着いているわけですが、この令和の時代にのうのうと生きる私からしたら、絶句してしまうような苦労苦難の連続。菊之助や仇討ちについて聞き回っている武士とは全く違う身分の者で、多くの武家出身の者は生涯知ることでないであろう彼ら庶民の(庶民というより下の)暮らしや人生を、菊之助たちが生身の交流を経て知ることになったというその事実の尊さに気づいたとき、なんとも言えない感動が心に広がりました。
ひとり、またひとりと語り手が代わるごとに、菊乃助の仇討ちの真相が少しずつわかってきます。あれ、単純な仇討ちでもなさそうだぞ、とこちらが薄々気づいてきたところに、小道具の久蔵とその内儀お与根の章で、衝撃的な事実が明かされます。そして続く筋書の金治の章では、はっきりと事実が見えてきます。なるほど、やはりこれはただ恨みをはらすための、単純な仇討ちではなかったのだな、と。
語り手5人は、いつ野垂れ死んでいてもおかしくないという境遇にも関わらず、恨みや妬みなどの負の感情に支配されずに、生きるために、なされるがままにここまでやってきていて、それでいて彼ら自身にとって悔いのない生をきちんと生きている。武士の世界という狭い了見でしか物事を見ていなかった菊之助が彼らにどれだけの刺激を受けたか、そしてそんな彼らだからこそ、菊之助が武士という肩書に囚われすぎてどうしようもなくなっているところを助けたかったのだと、固く結びついていた紐がはらっとほどけるように理解できました。
心に残る良い読書になりました。
**********
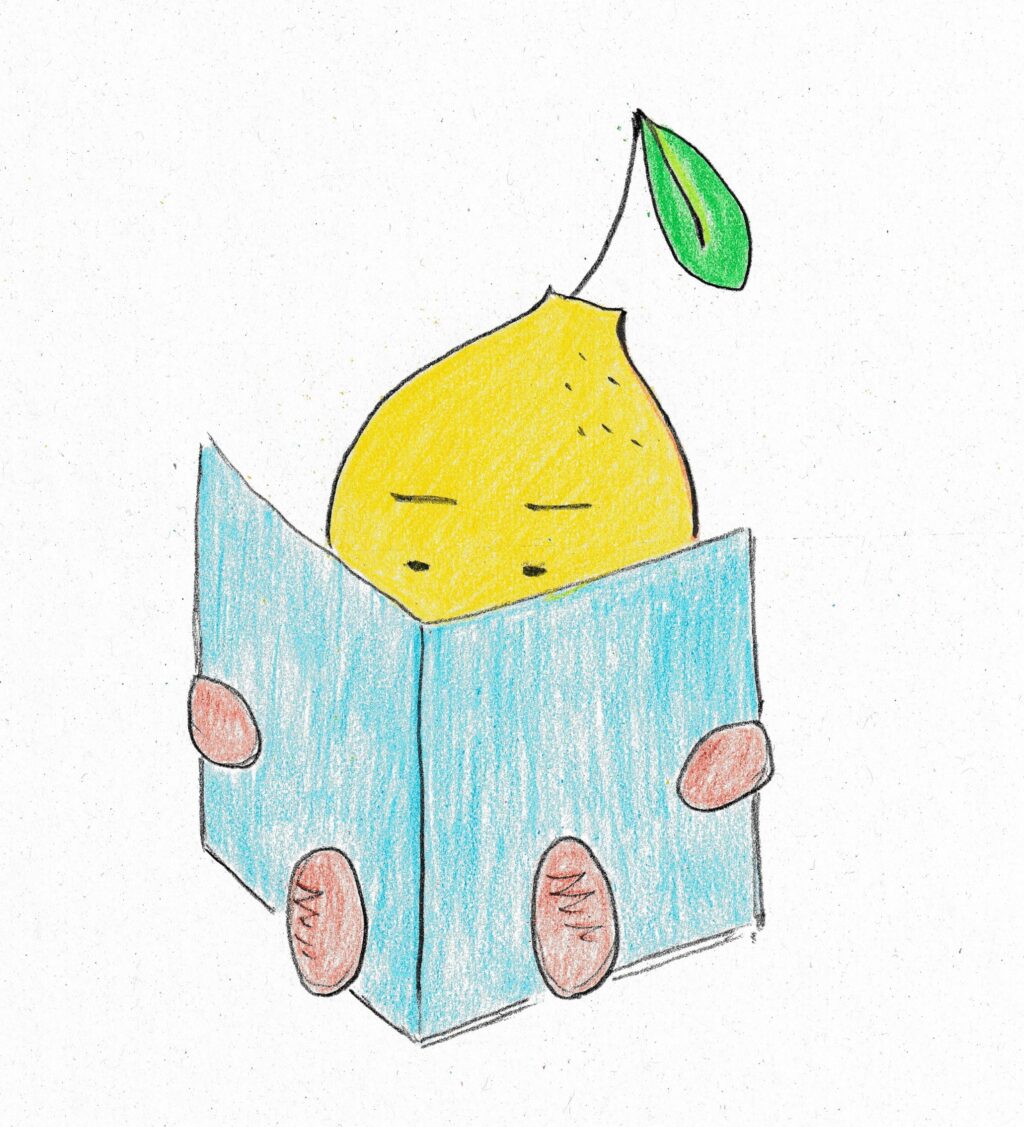
いや~とってもよかったです。一冊で、武士の物語も、市井の人々の物語も堪能できてしまう。同じ時代同じ場所に生きていた階級が違う者同士の交流って、きっとあったはずで、それがこんなにも心温まるものだったらいいな~と、歴史としては残らなかったエピソードに思いを馳せたりしました。みなさんの評価が高いのが納得です。
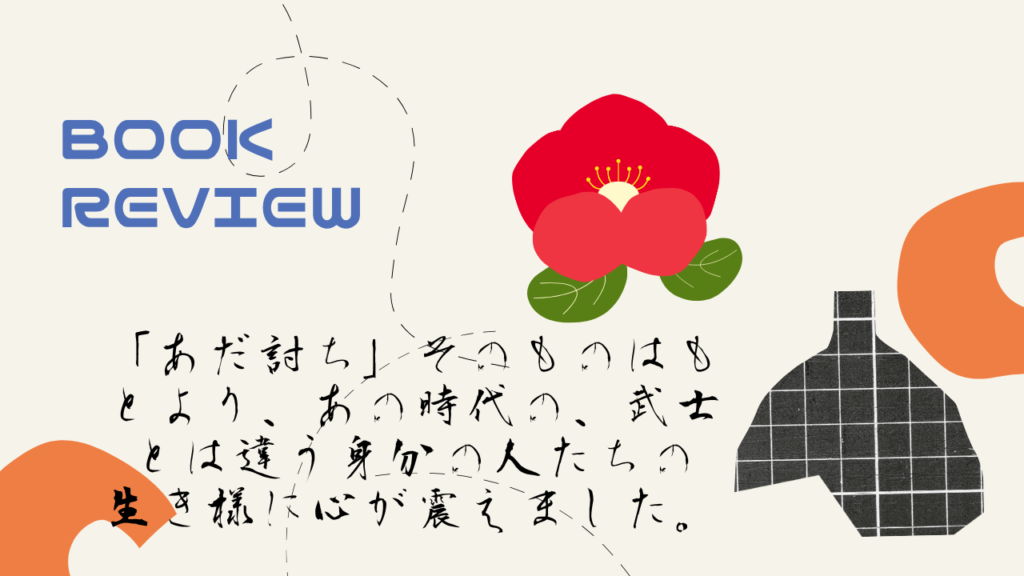


コメント