**********
梨木香歩さん、こんなところにまで達してしまわれたんですね、と深く深くため息をつくように思ってしまう作品でした。
以前、どこかに掲載されていたインタビューで、この「海うそ」という作品を境に、何か大きく変わったというようなことを語っておられた記憶があります。この記憶もかなりあやふやなのですが、それからなんとなく、この作品は、重要な作品だと自分の中で位置づけてきた気がします。そういう先入観で読み始めたのですが、それが確信となるような、なんだかどっしとした重みのある作品でした。
昭和の始めに、人文地理学研究者の秋野が研究のために訪れる南九州の遅島は、読むにつれて実在の島としか思えなくなり、思わず地図を開きたくなりましたが、やはり架空の島とのことでした。その地理的なこと、文化的なこと、伝統などがあまりにもリアリティ溢れるので、作者がどれだけ、たくさんのフィールドワークや文献にあたってきたか、想像するだけで到底かなわないと思ってしまいます。(参考文献については、巻末のリストを見たらその多さ、難解さが一目瞭然です。)
ひとりの人間がとうてい抱えきれるものではない大きな喪失を抱えて、主人公秋野は、上司である教授の研究を引き継ぐように遅島にやってきたわけですが、その喪失と否応なく向き合いながら研究が進んでいくように感じられます。島の青年梶井と島の奥深くにフィールドワークに出るところは圧巻でした。フィールドワークなんて経験したことがないけれど、一緒に島の奥深くに分け入った気がするし、明治の廃仏毀釈によって、今は遺跡となった大寺院(ここにも「喪失」があります)には、恐ろしいくらいの過去の想いを感じました。
そして、遅島に関する論文は結局完成をみないまま、50年の時を経て、老いた秋野が再び遅島を訪れます。この後半に差し掛かった時、「喪失」はこのようにも描写されることになるのか、と思わず「うまいな、すごいな、さすがだな」と思いました。遅島は本土と橋でつながり、観光地として再開発が進んでいました。かつて青年梶井と歩いたあの島ではなくなってしまうという焦り、そもそもあの時知り合った島の人たちはみな亡くなっているという現実による「喪失」。
これまで、こういった田舎の村や島のニュースを見聞きしても、どこか別の世界のように感じていましたが、前半の島での研究の描写を読んで、一緒に体験したような気持になっているこちらにも、この島の変化は思い出を抉られるような辛さがありました。
秋野にとっては、島の変わりようが、神聖な自然や遺跡にまでにおよぶ人間の手の入りようが、ひどく堪えますが、これも時代の流れだ、変化はしょうがないと、諦めの境地ではなく、「喪失とは、私のなかに降り積もる時間が、増えていくことなのだ」との思いに行きつきます。実は50年前から答えは出ていて、それでも居ても立っても居られない状態でこの島に来て、島を歩くことで、どうにか喪失と向き合い、50年という月日というより人間としての老いが、やっとその答えを受け入れられたのかな、と、そんなふうに勝手に解釈しました。
作者がこの作品に込めた思いをどれくらい読み取れたか。全く自信がありませんが、またいつか、きっと読み返すことになるだろうと思える作品でした。読むたびに深く理解できるのか、それともまた違った発見があるのか、今から楽しみです。期待以上にいい作品でした。
**********
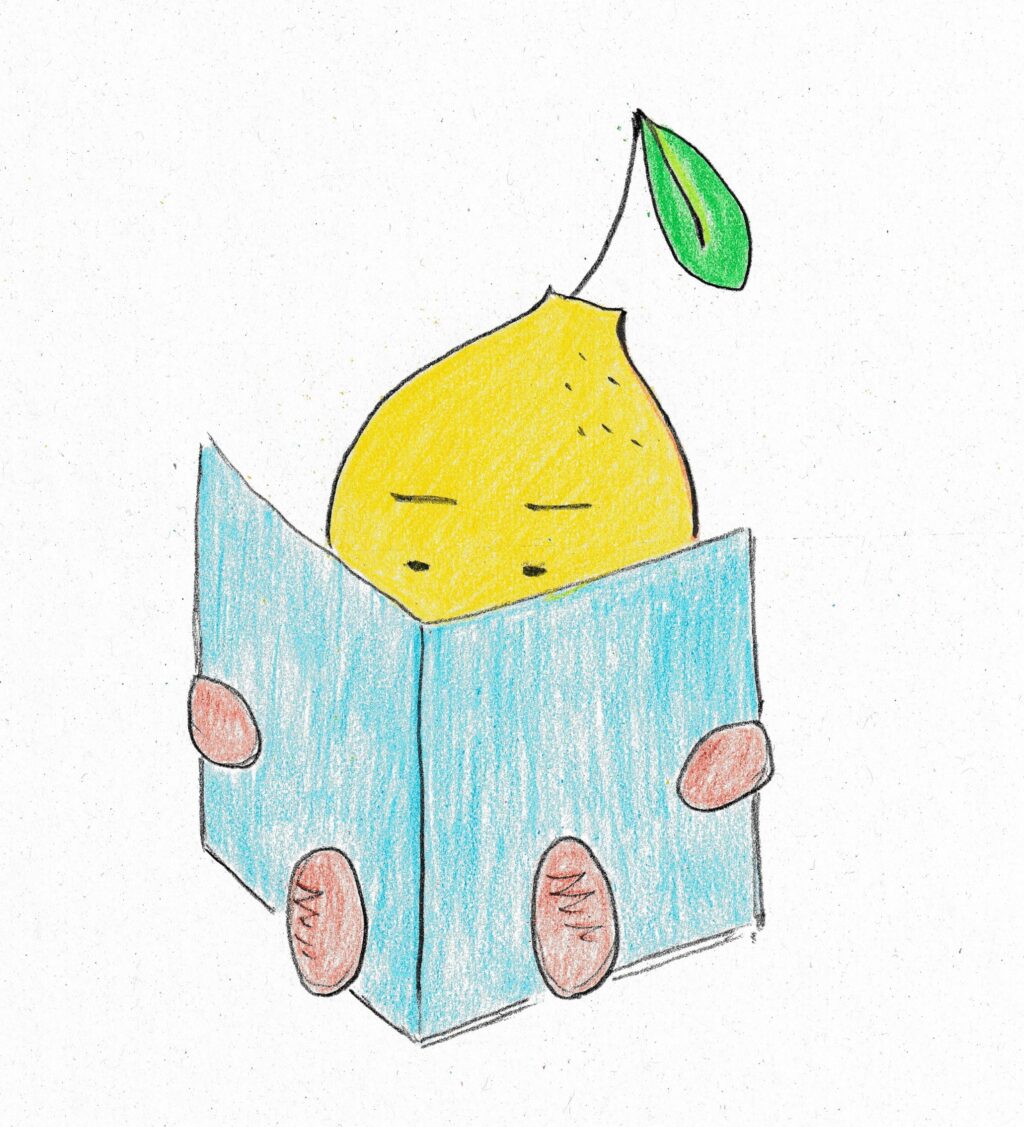
考えたくはないけれど、生きていればいつかきっときてしまう「喪失」に耐えられなかったら、この本が何か指針のようなものになるかもしれない、と思いました。
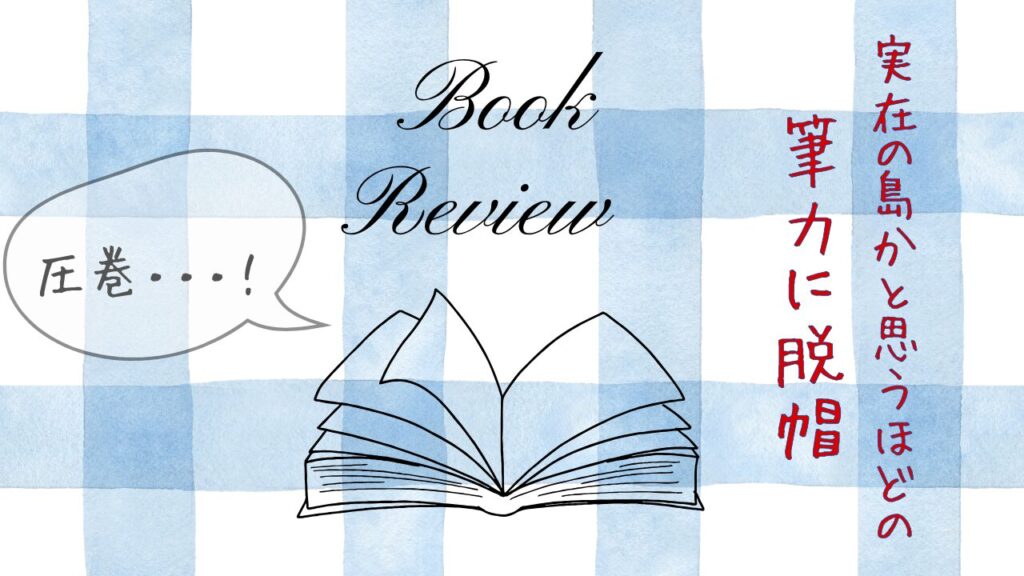


コメント