**********
もうかれこれ5~6年前になりますが、娘がピアノを習おうと体験レッスンに行った時に、先生が取り出された教則本が、昔使用していた「バイエル」ではなかったことから、「はて、バイエルとは何だったんだろう?」と思ったことがきっかけで、ずっと読みたいと思っていた本でした。読みたい本が次から次に出てくるのでつい後回しになっていましたが、ずっと心のどこかにひっかかっていました。その体験レッスンの時、私が思わず「バイエルじゃないんですね」と言うと、「もうバイエルはあまり使われていないと思いますよ」というようなことを言われ、さらに興味が湧いたのでした。ちなみに、それから娘はピアノを始め、ずっとこの先生のもとで「バスティン」を使っていました。最近ようやく全てのバスティンを終え、「ブルグミュラー」に入るというところで、発表会の曲を優先してやっているため、教則本は少しお休みしているところです。娘に続いてピアノを始めた息子は絶賛バスティン中。縦型のテキストに入りました。
話が逸れましたが、昔私がピアノを習っていたころは当たり前のように「バイエル」を弾いていて、まわりの子もみんなそうだったという記憶があったので、「もうバイエルは使わない」という先生の言葉にちょっと驚いた記憶があります。
ただ、ここで正直に書いておきますと、私がピアノを習っていたのは小学生までで、引っ越しが理由の空白期間もあったので、正味4~5年習っていたかどうかというところです。その後社会人になって再度習い始めましたが、結婚や出産を機にピアノを弾くことからは遠ざかってしまっている今現在です。レベルとしてはソナチネの途中でやめたので、今はブルグミュラーも満足に弾けるか、はなはだ怪しいところ。さらに楽典という点になると、ほとんどきちんと勉強していなかったので、子どもたちのレッスンについて行っては、例えば調号のつけ方などを知って「へーーー!」と楽典の面白さに気づいた次第です。
前置きが長くなりましたが、なぜバイエルが使われなくなったのか、いや、そもそもバイエルって?人?から始まった私の疑問にドンピシャに答えてくれる本書でした。
本書の作者は当時奈良教育大学で教員をしておられた安田寛先生。音楽学者とのこと。作者も私と同じような疑問からバイエルについての研究を始めたようでした。本書のはじめでは、フェルディナント・バイエルという名と、生没年月日くらいしかわかっていない状況でした。ピアノを習うといったら当たり前のように「バイエル」が長年使われてきたのに、バイエルについては何もわかっていないという不思議な状況。バイエルの祖国ドイツの文献でも数行の記載しか見当たらない状況でした。
そして、私が驚いたようにいつの間にか「バイエル批判」が世間ではびこっていたことについても触れられていました。1990年代以降にじわじわと広がっていったとのこと。もしかしたらバイエル批判が始まった頃、私はまだピアノを習っていたかもしれないと思うとなんだか切ないような感慨深いような何とも言えない気持ちになりました。
さて、バイエルについて調査を始めた作者ですが、なかなかバイエルという人物を特定できません。ならばということで、バイエル教則本が誰から日本にもたらされたのか、なぜ日本でここまで広く長く(100年以上!)教則本として使用されるようになったのか、などを調べていきます。詳細はぜひ本書で確認してもらえたらと思いますが、さすがは学者というところで、まるで謎解きのように色々なことがわかってきます。そして、バイエルの教則本としての構成自体にも疑問点がいくつか出てきます。ここらへんは、ピアノ(音楽?)に明るくないとあまりよく理解できないと思いますが、実は併用曲集として作品101bisが存在していたことや、番号付ではない曲「番外曲」があり、実はバイエル本体はこの番外曲であり、番号曲はいわばお楽しみ曲だったのではないかなど、これまでの常識が覆るような考察が出てきたりします。ん?なんだなんだ、どういうことだ?と興味をひかれつつも、やはりピアノに詳しくない私にはよくわからないことも多々あり、ちょっと中だるみしました。作者自身もこれまでの研究結果により、バイエルは仮名ではないか、ひとりの人物ではないのではないか、複数人で作り上げた教則本ではないかなどという疑いをぬぐえないでいました。
あぁ、ちょっと眠たいわ、飽きてきたわ、というところで、やっとフェルディナント・バイエル本人にたどり着きます。それこそ、まさに劇的というか、神がかっているのですが、これまで「1803年生まれ」と信じていた生年を「1806年」と間違えてドイツのアルヒーフの職員さんに伝えたことで、するすると糸をたどっていくようにバイエル本人にたどりついていきます。ここで眠気が一気に覚めました。まるでちょっとしたミステリーのようでした。作者によってバイエルの正しい生年がわかり、その家系、そして第二次世界大戦でなくなってしまった墓地の跡地までわかったのです。さすがは学者さんです。今まで全く知られていなかったバイエルについてここまで解明できたというのは、すごい功績ではないでしょうか。ちなみに読了後、バイエルのWikipediaを調べてみると、本書で安田先生が調査したことそのままが記載されていたので、逆にいうと本書以上の研究はないということかもしれません。
ということで、長年使われてきた「バイエル教則本」のフェルディナント・バイエルはちゃんと実在した人物だったということ、長年日本で親しまれてきた理由のひとつは「バイエル」という冠に価値を感じたたくさんのいわば改訂版が出版されるという独自の発展を遂げた結果だったということ、バイエル自身の時代から評価が低かったのは、当時バイエルがたくさん生み出したいわゆる大衆音楽にまだ理解がなかったからだということ、などがわかりました。
また、なんだかんだ結局私が一番こだわっていた、なぜバイエル批判が高まったのかという点については、本書を読んでの完全な私見になりますが、バイエル文化が独自に開花していった日本において、そもそもバイエルが意図したような使われ方をしていなかったのではないか、そうでかったとしても、欧州に遅れながらも、その他に適切な教則本があると日本人が気づいたこと、つまり時代の流れ、ピアノ教育の必然的な変化だったのではなかと思いました。
つまり、私の中では、安田先生同様、バイエルは偉大な音楽家であり、もっと広く知られてよかったと思う歴史上の人物でした。(バイエル教則本があまり使われなくなった今としては難しいでしょうが・・・)
本書はただ、研究結果を書き留めたものではなく、安田先生の研究旅行先でのあれこれも楽しめるエンターテイメントでした。調査過程の安田先生の悲喜こもごもの描写もとっても面白いですよ。読んでいるだけのこちらもドキドキしました。音楽に興味がある方はぜひ!とおすすめできます。
(そんなにバイエルって楽しくなかったかな、と逆にもう一回弾いてみたくなりました。実家にまだ眠っているかな、「赤バイエル」と「黄バイエル」・・・)
**********
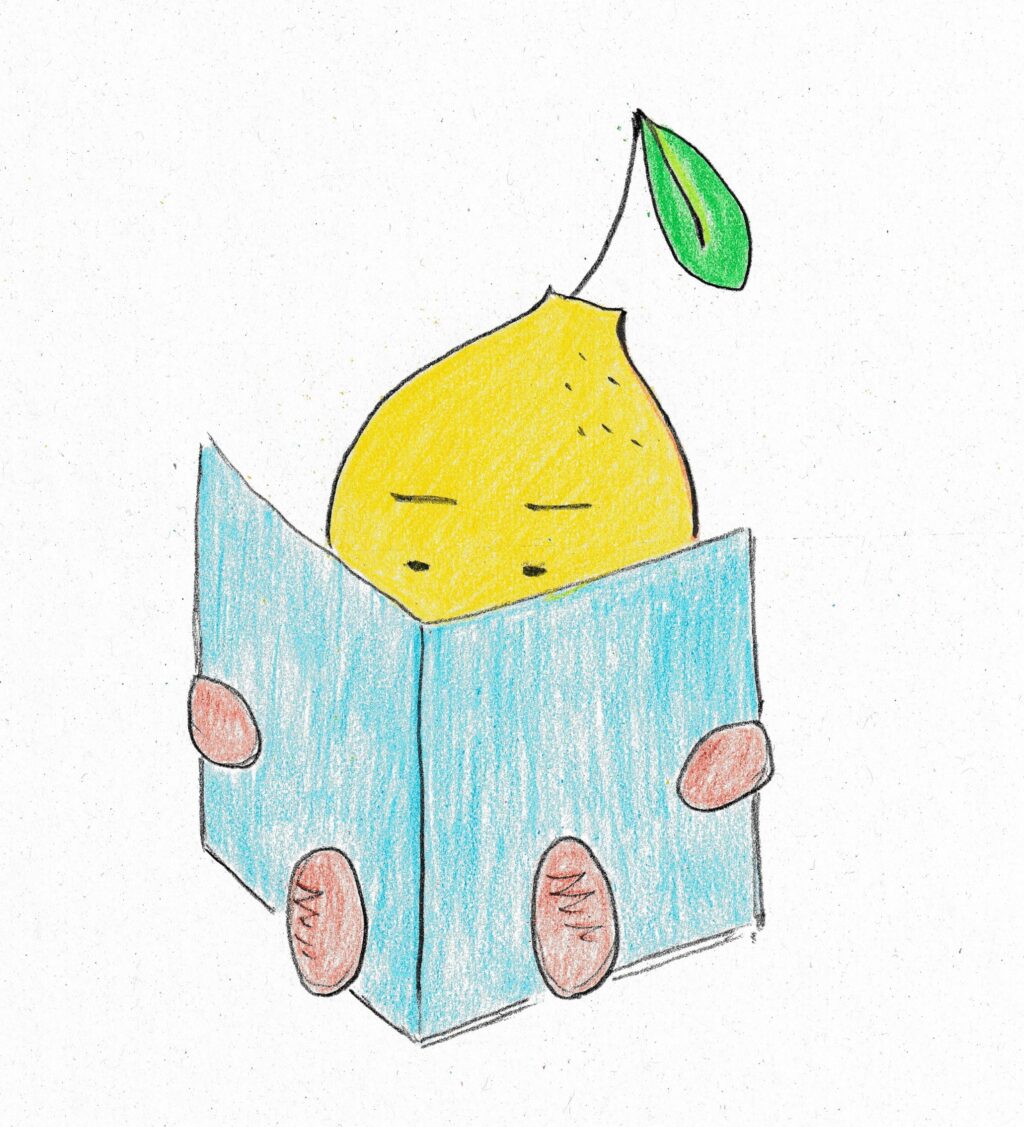
すごく面白かったです!いずれにしても、後世にまで名が残るってことはやはり何か秀でたところがあって、残るべき作品があったということですね!
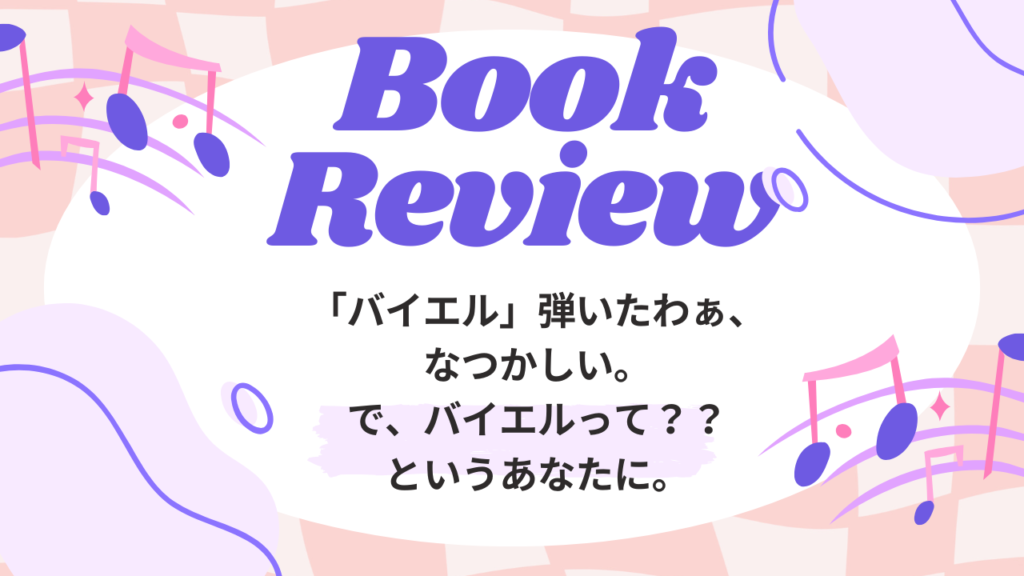

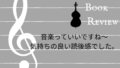
コメント