**********
たとえ私自身が東大京大に現役で入れるような素晴らしく賢い頭脳の持ち主であったとしても、私は絶対に医者にはなれない、なりたくない、と思います。その多忙さもさることながら、まさしく本書の一止のように患者に寄り添うだけの器の大きさだとか、精神的なタフさ、賢明さがないから。だからこそ、医者という人たちには本当に頭が下がる思いです。その思いが改めて強くなった物語でした。
本書が前に話題になっていたのは知っていたので、タイトルを見ただけで、「あ、読みたかったやつ」と声に出してしまいました。今回も職場の人が貸してくれて、ついつい読みそこなっていた本が読めたので感謝!
本書の主人公は松本にある本庄病院に内科医として勤務する栗原一止。夏目漱石の「草枕」を愛読し、言葉遣いもどこか古めかしい「変人」です。が、同僚の医者や看護師はもとより、患者からも評判のいい、素晴らしい医者というか、人でした。
一止の細君・ハル、友人・次郎、上司の大狸先生に古狐先生、看護師の東西さん、患者の安曇さん・・・出てくる人がみんなみんないい人で温かい。こんなの現実的じゃないし、あり得ない。なんて野暮なことを言うのはやめておきましょう。この物語はこの温かさが良いのです。
一止は、大学病院からの誘いを受け、悩みに悩みます。それは、同じ医療に携わるという仕事でも、今の本庄病院と全く環境が違うからです。大学病院に行けば、最先端の医療が学べる、高度な医療が学べる、色々な症例について研究のような勉強ができる・・・でも、本庄病院のように、患者さんひとりひとりを最期まで診てあげることができない。難しい選択です。一止が、患者さんと、「医者と患者」という関係ではない、心からの交流をし、看取っては立ち止まり、また進み出し、を繰り返しながら悩む姿が、私には頼もしく感じられました。向上心があるからこそ悩むのであって、決して現状に甘んじていない、頼もしいお医者さんの姿でした。
松本という街の描写も良かったです。大学時代の友人が、地元松本に帰って就職した折に、数人の友人たちとわいわい訪ねて行った思い出がある街です。松本城は圧倒的な存在感で、街全体は落ち着いた良い街だなと思ったことを思い出しました。
最後、一止の悩みは、一止の気づきで、解決します。その気づきが良かったです。
「迷うた時こそ立ち止まり、足元に槌をふるえばよい。さすれば、自然そこから大切なものどもが顔を出す。そんなわかりきったことを人が忘れてしまったのは、いつのころからであろうか。足もとの宝に気づきもせず遠く遠くを眺めやり、前へ前へすすむことだけが正しいことだと吹聴されるような世の中に、いつのまになったのであろう。」
迷ったときには、一旦立ち止まってみよう、と思いました。
さらに、上橋奈穂子さんの解説が良かったです。上橋さんの解説が私の感想のすべてを代弁してくれているかのようでした。
**********
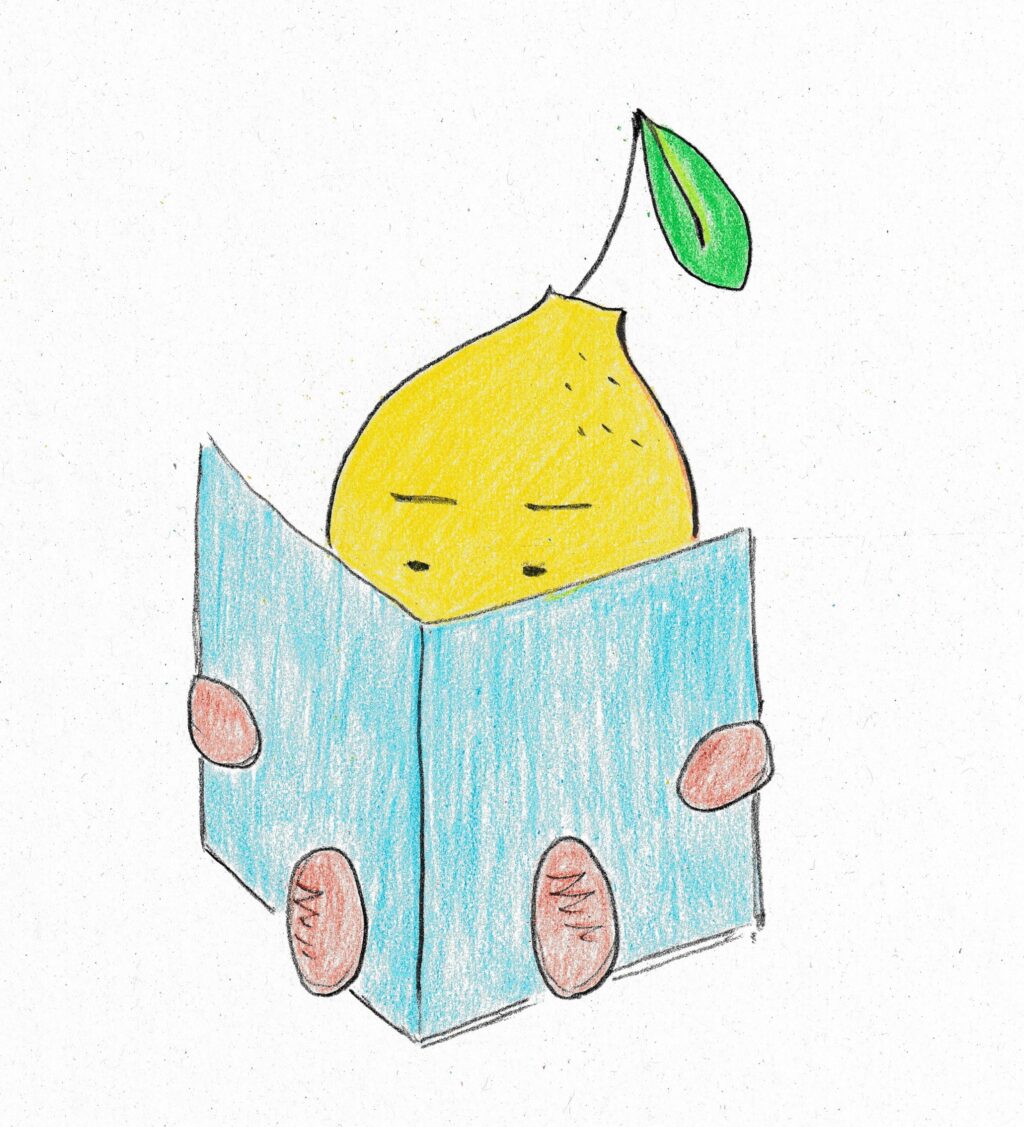
こういう温かい物語を読むと、言い古された言葉ですが、心が洗われるようでございます。読んだ後、個人的には看護師の東西さんがとても気になりました。一止にとって、頼れる良き同僚であり、後輩に対しても良い先輩のようでなんて素晴らしい人かしら、そして一止に実は想いを寄せている・・・としたら切ないなぁ、などと考えてしまいました。
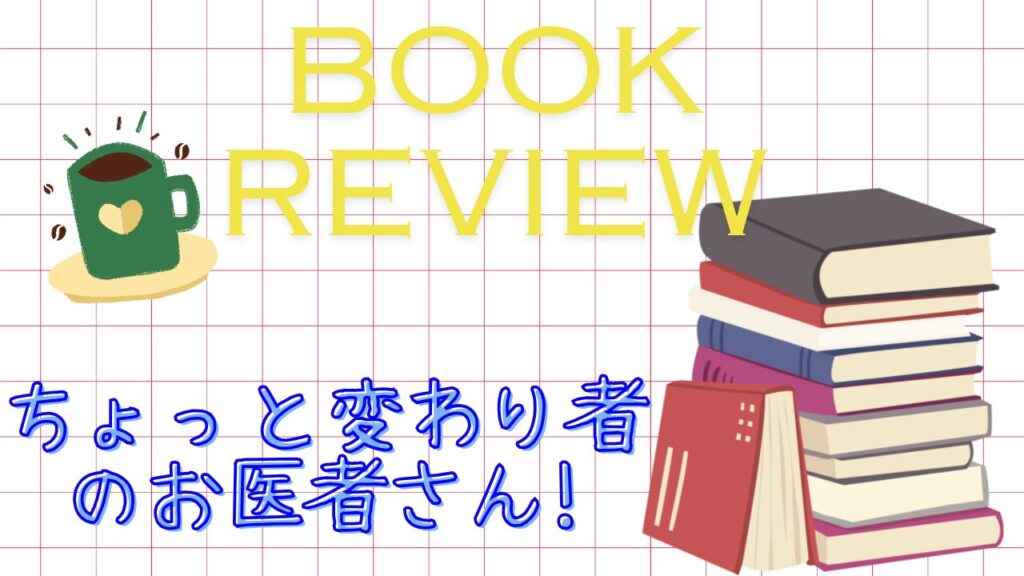


コメント