**********
大学卒業後十数年やってきた仕事を燃え尽き症候群のような感じで辞めた主人公が相談員の正門さんからまず紹介されたのが、「みはりのしごと」。
正門さんに「一日コラーゲンの抽出を見守るような仕事はありますかね?」と希望を言ってみたら出てきたのがこの仕事だったのですが、たやすいように見えてたやすくない。まさに「この世にたやすい仕事はない」を一作品目から痛感することになりました。他人の生活をモニターでずっと観察するという、地味な絵面ながらも、なんだかクスっと笑ってしまうところがあったりして、妙にハマってしまうお話でした。主人公がマテ茶の茶葉を手に入れられなくて悶々としているところで、監視対象者がマテ茶の茶葉を入手していて、ちょっとした怒りさえ覚えてしまうところとか、ブフっと笑ってしまいました。派手なお話じゃないのに続きが気になるお話で、さすが津村さんだと思わされました。結局主人公はこの仕事の契約更新を断るのですが、その決断に至るところの心情描写にすごく説得力があって、たぶん10人中10人が「うん、更新しない」と思ってしまうのではないでしょうか。
そして、次に正門さんから紹介されたのが、「バスのアナウンスのしごと」。アホウドリ号という循環バスの中で流す広告アナウンスの原稿を書いて、録音して・・・という仕事なのですが、ちょっと奇妙なことが起こるんです。この二作品目から、「サキの忘れ物」を読んだ時の感じを思い出しました。特に「河川敷のガゼル」を思い出しました。「いや、ちょっと待って。なんかちょっとおかしい。」と冷静に考えると思うのだけれど、あまりにも淡々と「いや、どこもおかしくないですよ。」という体裁で、つらつらと物語が続くので、不思議と普通が、奇妙と普通が、グラデーションのように境目なくそこにあるのが、なんというか、まさしく津村さんという感じがするし、うまい、と思うのです。
次は、バスのアナウンスの仕事が認められて、「おかきの袋のしごと」をすることに。おかきひとつひとつの包装に「国際ニュース豆ちしき」などいくつかのテーマにそって、豆知識的な情報を印刷するので、その文章を考えるという仕事。このお話はもう、主人公の仕事に対する心の動きというのか、機微というのか、そんなものがすごくうまく文章として表現されていて、結局主人公はこの仕事を任期満了的に辞めてしまうのですが、そこまでの過程がすごく納得のいくものでした。いやぁ、うまい。
さすがに正門さんに対して申し訳なく感じてきた主人公は、デスクワークにこだわらないといって、次の仕事「路地を訪ねるしごと」を紹介してもらいます。これはちょっと暗い影が付きまとう仕事でした。なんだか怪しげな活動をしている自称ボランティアグループの張り紙を、主人公を雇った盛永さんが作った張り紙に切り替えていく仕事なのですが、その怪しげなグループの怪しさといったら!紆余曲折あって、このグループがやっている集会(?)に潜入するのですが、その運営側の人たちについてこんな表現があります。「・・・どの人もなんだか妙に大きい黒目が虹彩の部分に滲み出しているようで、焦点が合っていないような、合いすぎて違和感があるというような、異様な目つきをしていた。」いや、もう絶対この人たちいかんことやっとるやん!と。この仕事で発揮される主人公の仕事に対する変なやる気というか使命感も、ちょっと危うさをはらんでいる気がして、終始不穏な空気が立ち込めるお話でした。不思議なんだけれど、どこか現実的でもあるなかなか感じることのない読後感でした。いやぁ、うまい。(←語彙力よ)
「路地を訪ねるしごと」は本書で初めて主人公の意思からではなく、終わってしまった仕事でしたが、次なる仕事は「大きな森の小屋での簡単なしごと」。そのままなのですが、大きな公園内の小屋につめて、周辺を散歩して見回る仕事です。合間に小屋で内職のようにチケットのもぎりのためのミシン目を入れるという業務もありますが、これまたちょっと不穏な感じがしてくるのです。なんと前任者には「幽霊がでる」と言われるし、実際に小屋を不在にした後に戻ると、首をかしげてしまうことが起こっているのです。
最後の最後に主人公がこうやって転々と職を変える前にしていた仕事が何か判明します。個人的に一度考えたことのある職種だったので、「おぉ」と思いました(今の私の仕事は全く関係ありませんが)。「燃え尽き症候群」という言葉を思い出して、「さもありなん」と思ってしまいました。「大きな森」での仕事をある一定期間したら、元の職種に戻っていく人が多いという箱田さん(大きな森の小屋のしごとでの上司的存在)の言葉に主人公の未来が見えました。そして、この職を転々としていたことが全て無駄ではなかったとでもいうように、次の仕事への道筋が見えてきます。
いや~、面白かったです。個人的に、大学卒業後ずっと続けている現職を早期退職して、違うことをしたいな、とぼんやりと考えているので、なんだか、どんな仕事でもできそうな気がしてきました。
やっぱり、こう現実的にちょっとおかしくないかい?と思ってしまうことが、すっと現実になじんでいる感じが独特で、その世界線にいる主人公の心の動きがすごく丁寧に描写されていて、それでいて、クスっとニヤッとしてしまうとこもわりと頻発して、何が言いたいかというと、津村記久子さんってすごいな、ということです。津村作品は本書の前に「水車小屋のネネ」を読んで、これまたえらく感動したのですが、それとはまた違う趣の話で、でもやっぱり津村作品で、まるで私が津村記久子という逸材を見つけたかのように、うれしくなる読後感でした。
いや~、津村記久子さん、やっぱり推します。梨木香歩さんの作品は全部読むと決めていますが、津村さんの作品も全部読もう!
**********
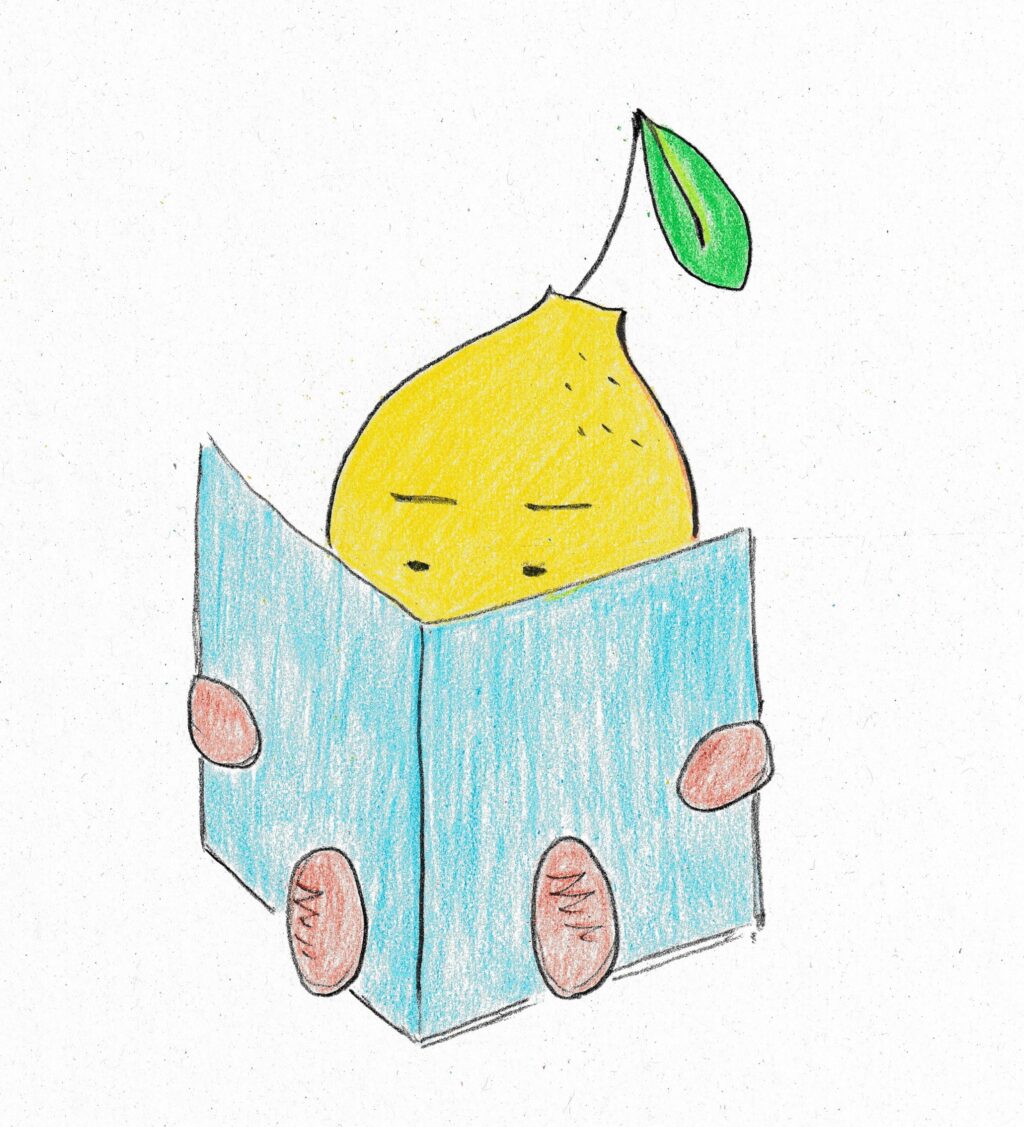
「5回も転々と職を変えている」という言葉だけだと、あまりいい印象はないけれど、どれもこれも主人公が仕事に対して誠実で、最後には5つの職を経験したからこそ、元の職種に戻るのだろうな、という未来が見えて、とても良い読後感でした。

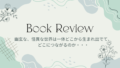

コメント