**********
人間というものは、錯覚の動物で、だれも、そのバイアス(思い込み、錯覚、偏見・・・)の影響からは逃れられないからこそ、日常で陥りがちなバイアス=思考の穴について、それにどう対抗していくのかを示した本でした。
自分のまとめのためにも、本書にあげられていたバイアスとその対処法(矢印の先が対処法)について箇条書きしてみます。
・流暢性の魔力
頭の中で容易に処理できるものに対して人は自分の能力を過信する。
→流暢性効果で過大評価となった自分の自信や知識はやってみることで軽減される。
ダンスなら踊ってみる、知識なら説明をしてみる。するとできないことがわかり、人間は謙虚になる。
意見が異なる人と対話することが社会にとって重要である。反対意見の人に説明することにより、知識の穴や議論の欠如を自覚する。
やってみることができないことは、50%増しで計画をたてる。
・確証バイアス(筆者によるとこれは最悪の認知バイアスらしい)
自分が信じているものの裏付けを得ようとする傾向。自分が正しいと信じていることが否定されかねない情報に目を向けないこと。
信じたとたん、信じたように行動し始めるという悪循環。
人間はみな平等に扱われるべきという道徳の原理の根幹が侵害される。
メリットは、無限の選択肢から十分だと思えるものに出会ったら探求をやめられるから、幸福度は高まり、順応性は高くなる。
→克服するにはむしろ確証バイアスを利用すればいい。ひとつではなくふたつの相容れない仮説をたてて両方の実証を試みる。質問の切り口を反転させて問う。
・関係のないことに罪を着せてしまう
類似性を求める欠陥。小さな原因から大きな結果が生まれるとは考えないこと。
十分性が十分な原因を突き止めたら他の可能性を排除してしまう。
ある現象が起きた原因が一つ明らかになると、原因となりうるその他の要素は自動的に考慮されなくなる。「普通じゃないこと」が原因だと思ってしまう/「しなかったこと」より「したこと」のせいにしてしまう/「最後に起こったこと」が原因だと思ってしまう/「ほかのことができたのに」と考えてしまう
→反芻は問題解決の妨げになる。答えが見つかりそうにない問題に建設的に取り組むには、そこから距離をとる。
答えを一つに絞ることは不可能なうえに無意味だ。
原因に執着するのをやめたら離れた視点からその出来事を見つめられるようになる。そうなれば、自責や後悔といった負の感情から解放される。
・危険な「エピソード」
自らの視覚、触覚、嗅覚、味覚、聴覚で感じ取れるものに基づいて思考する。抽象的な統計資料などが無視される。エピソードの影響を過剰に受ける。
→それを避けるために以下3つが合理性を高めてくれる。
大数の法則
平均への回帰
ベイズの定理
・「損したくない!」で間違える
ネガティブな情報や出来事を重視してしまう。保有効果もこのひとつで、持っているものを失いたくない。
→フレーミング効果(ネガティブな質問をするかポジティブな質問をするか)。
保有効果の影響をうけないようにする(なんと、こんまりさんが出てきた!)。
・脳が勝手に「解釈」する
人には自分が信じるものを信じ続けようとする傾向がある。
→解釈にバイアスがかかることは簡単に止められないと認識する。
・「知識」は呪う
自己中心性バイアス。他人の視点で考えたり、他者を思い合ったりするだけでは必ずしも事実を正確に認識できるようにはならない。(小説を読むこと自体に効果はあるが、何年にもわたって膨大な数を読まなければならない)
→いちばん確実なのは「直接、聞くこと」。他者の心を読もうとすることが大きなストレス。真実を集めることだけが互いの理解に確か。
・わかっているのに「我慢」できない
未来に手にする結果の価値を、私たちはいかに不合理に割り引くか。
→「未来を信じる力を高めること」が解決策のひとつ。
先のことをできる限り具体的に想像する。
ただし行き過ぎた自己管理はよくない。「結果に飛びつかず、過程を楽しめ」。
こうやって列挙してみると改めて、これらを意識するのはなかなか大変だと思いました。あとがきであるように、新しい思考というものはなじむまでに時間がかかるもの。読みっぱなしではなく、折に触れて、この思考はどのバイアスだったかな、どう考えたら良かったかななどと、トライ&エラーしていかないといけないと思いました。
そうやって日常において思考していくことは大変だけれど、人間はすべてを論理的に判断できるようには絶対にならないのだからこそ、どういったバイアスがあるのかを知っておくと、より生きやすくなるだろうし、作者が認知心理学に求めるように、「世界がよりよくなる」のだろうと思いました。
それにしてもこのイェール大学での授業はとっても面白そう!こうやって書籍で読めたのは、良かったけれど、授業として受けることができた学生が羨ましい。
**********
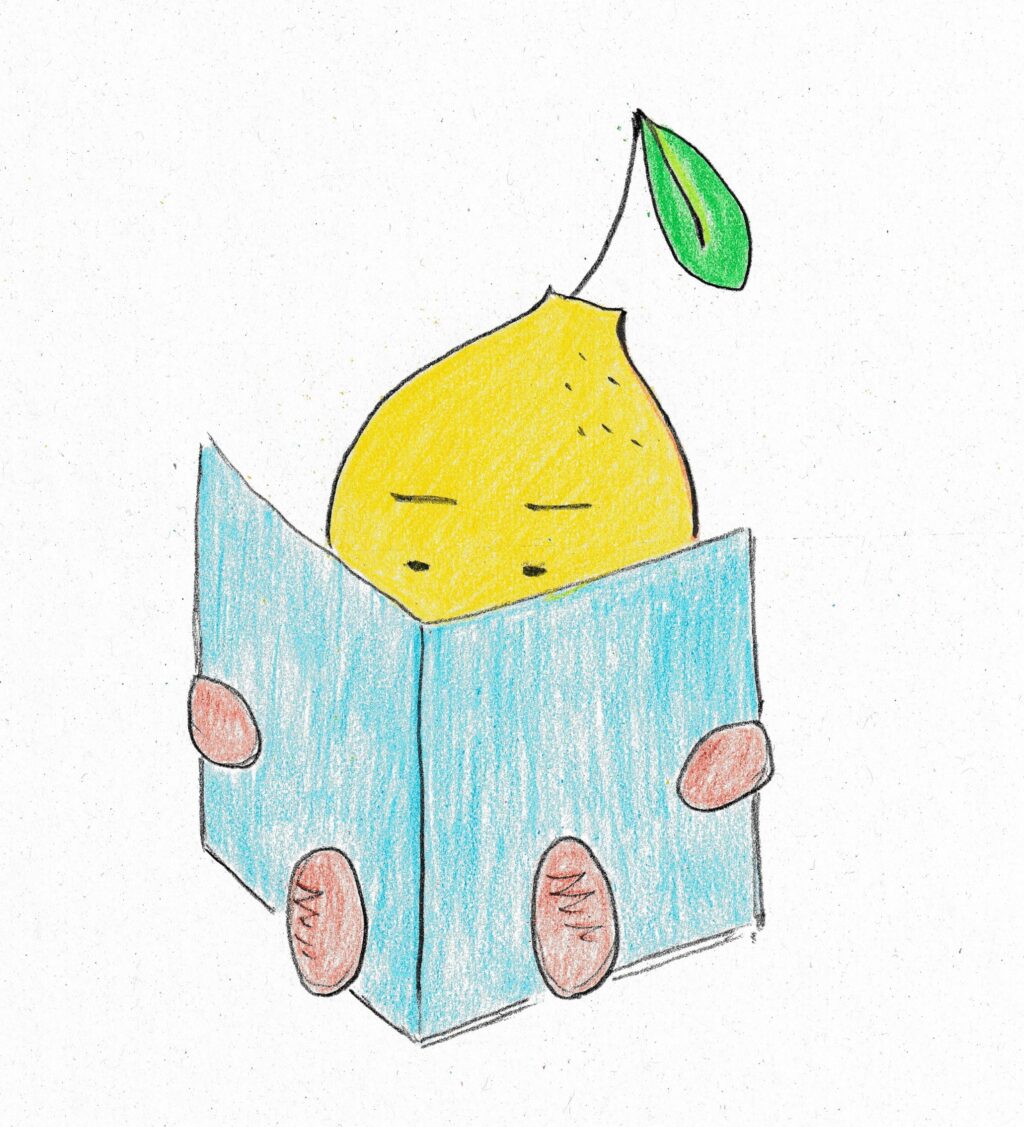
せっかくこの本を読んだのだから、「あぁ、この思考があの本に書いてあった”穴”だね」と自分の中で気づくことが日常で増えるといいな、と思いました。また一方で、バイアスによっては人間の進化にとって必要だったという説明も興味深かったです。
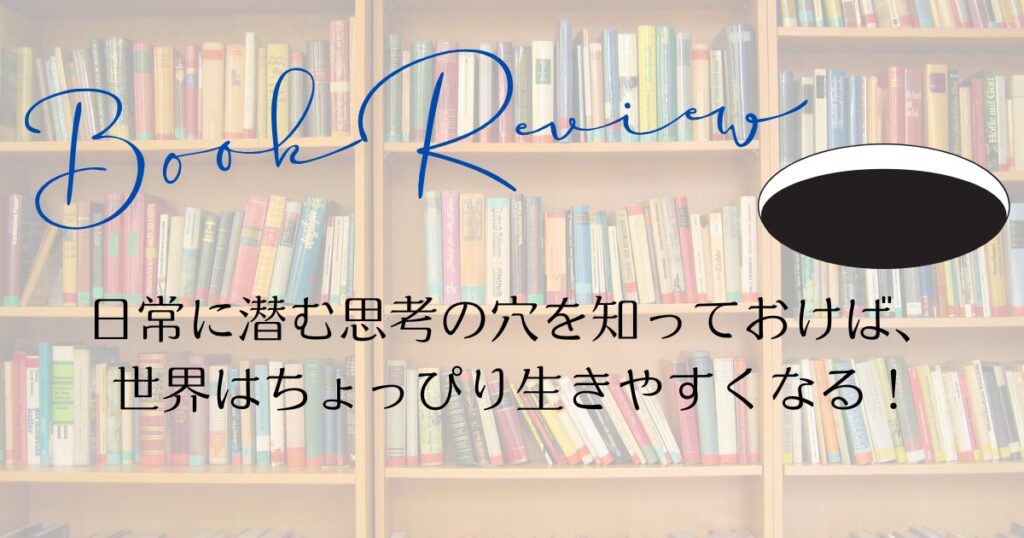


コメント