**********
もう、いっぱいいっぱいです。もう勘弁して、と思ってしまうくらい次々と困難な状況がふりかかってきます。主人公の宙にではなく、私たち読者に。
ネタバレしますよ、要注意!
宙には実母の花野と、育ての母の風海がいる。風海の夫の海外赴任をきっかけに花野と暮らすようになる・・・。
母親業はできないと周りも自分も思っている花野との暮らしはなかなかしんどい環境だな、と思ったのも本書半分くらいまでで、中盤からはもっともっとしんどい環境の人物が現れました。
彼氏の鉄太、同級生の廻、そしてヒロム・・・
大きなネタバレはしたくないので、書きませんが、父親代わりの佐伯だってそうだし、事情がわかってしまえば、花野も、風海もそうです。
こんなにも?!というくらいしんどい環境に苦しんだり、呪いのようなものを刷り込まれている人物たちを登場させてくるところに、少し詰め込みすぎだろっ!とツッコみつつも、ページをめくる手は止まりませんでした。他に読んでいる途中の本はそっちのけで、この本だけを一気に読んでしまいました。
色んな事が起こった読後となってしまえば、これは物語序盤だったな、と思いますが、宙とマリーが分かり合うところがよかったです。しかし、小学生でそんなに悟る?と思うほど、大人びた彼女たちの思考や話し方はちょっと悲しくもありました。結局、困難な環境が彼女たちを周りより一足先に大人にしているのか、と。それでも生きる知恵のようなものを既に掴みかけている宙もマリーも力強く生きていってくれるだろうと思ったものです。
そして、これも物語の序盤ですが、花野の柘植への依存や柘植の花野への入れ込みようなどは読んでいて嫌悪感しかなかったのですが、中盤以降、色々と事情を知った後から、別の角度で、フィルターなしに見ると、嫌悪感はなくなりはしないけれど、形や色を変えて違うものになった気がします。普通じゃない母親も、普通じゃない家族も、スキャンダラスなニュースも、自分を中心とした世界から自分の視点だけで見てしまうと、フィルターがかかって見えてしまう。宙の友達の奈々と同じ。と言っている時点で、また「この人はこういう人」と決めてかかっている。実際、奈々が成長し、変わっていっていることがわかるエピソードはあった。解説で寺地春奈さんが言っているとおり、わかりやすい属性にあてはめ、知っている気になって、決めつけてしまっては、その人の背後にあるものを見過ごしてしまう。気をつけなければと思いました。
それにしても物語の全編をとおして佐伯の存在が大きかっただけに、終盤での出来事は衝撃的でした。そしてヒロムの謝罪を暴力だといって諭すところはそのシーン全てが衝撃的でした。いや確かに。そんなこと考えもしなかった。もしも私がその場にいたら、両者にとっていたたまれない辛いことでありすぎて、どうしたらいいんだろうとオロオロするしかなかっただろうけれど、相手に赦しを強要している、しかも、突き詰めればそれは自分のために赦してほしいって言っているのだとしたら、確かに、被害者側にとっては暴力になりうるものかもしれない。すごく考えさせられたシーンでした。
ラストは良かった。これが亡くなった人も誰かの中で生き続けるってことなのか、と思いました。
美味しい食べ物が出てくるから困難な環境ばかりの物語にも温かさがありました。食べるって大事。人を想って料理をするって大事。そんな当然のこともまた思い返せた気がします。
解説にあったこの一文、「町田さんの作品を読む時は、感想と感情が忙しい。」いや、ホントそれ、と思いました(←語彙力よ)。
**********
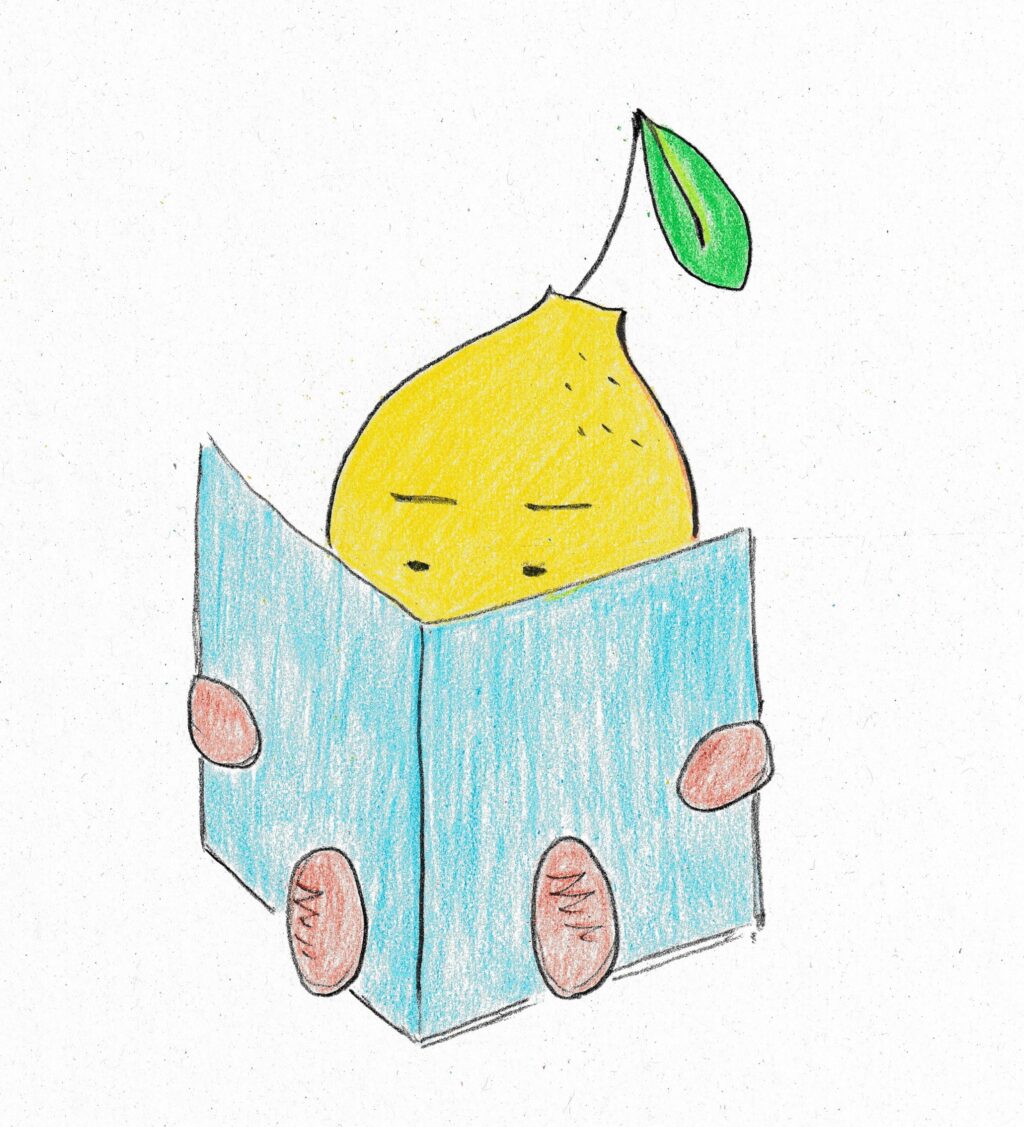
「ぎょらん」「52ヘルツのクジラたち」に引き続き、ヘビーな小説でした。本作の中心は大人に振り回される子どもたち、でしょうか。やはり絶対的に必要なのは、周りからの助けの手ですね。花野がヒロムの母を真っ正面から「助ける」と宣言するとこは清々しかった。そういう社会であるべきですね。
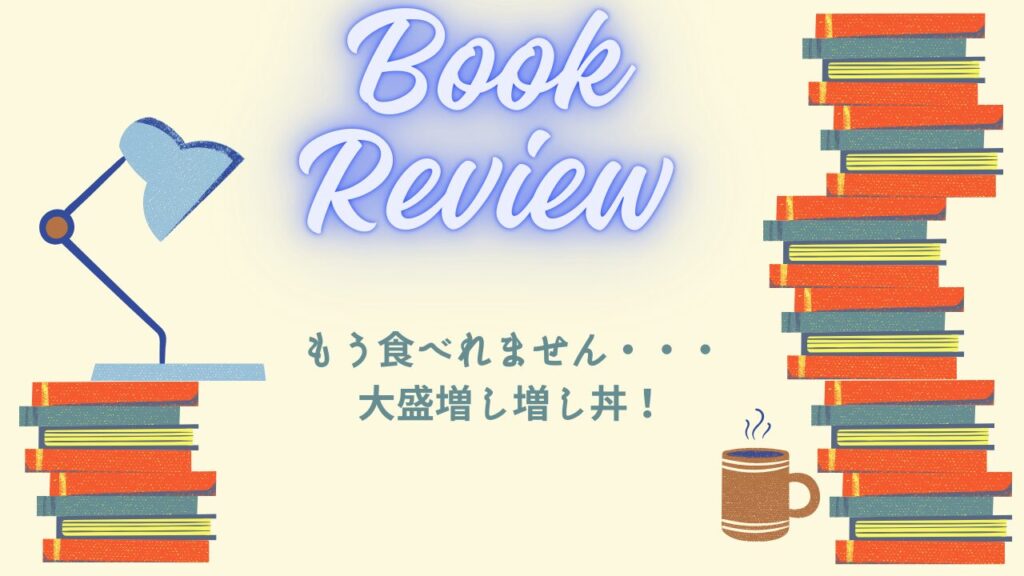


コメント