**********
中島京子さんの作品、読むのはこれが2つ目です。「小さいおうち」を読んでから、とっても気になっていた作家さんだったのですが、なかなか作品を手に取ることがなく・・・今回、読みたい本リストに入っていたとはいえ、ずっと放置していた本書をやおら図書館で借りた自分にも驚きました。本とのめぐり逢いも不思議なものです。きっと今だったんだと思います、この作品を読むのは。
さて、本書は「小さいおうち」とは全く趣の違う作品でした。読み始めてすぐに感じる違和感。どうやら、語り手は大人になってから自分の幼いころのことを思い出して書いているようだけれど、どうも現実的でないような・・・
9つの短編で構成されているのですが、どれも、この語り手が三歳から一二歳まで住んでいた町が舞台で、もっというと、小学校に上がってから学童保育代わりに放課後毎日通っていた喫茶店での出来事が語られています。語り手は喫茶店で赤い樽の中に入って常連客を観察したりして過ごしていたということや、常連客の一人である小説家に「タタン」と渾名をつけられたことなど、もうすでに現実的ではなく、読んでいてふわふわとした感覚に陥るのですが、物語がひとつ、ふたつ、と進んでいくうちに、これは現実と虚構の狭間の物語なのだ、という覚悟のようなものが芽生え、そう思うと、すごく興味深く読み進められました。
4つ目のおばあちゃんとの話で、語り手と喫茶店のつながりの原点がわかり、ちょっとほっとします。喫茶店の存在は、本当なんだ、と。
マスターの甥っ子の話で、これまでのすべての話が、幼いタタンの目を通して見聞きしたこと、心で感じたことだと思い当たると、現実と虚構というより、「子どもの世界」とか「現実と記憶の相違」というようなものを感じました。いずれにせよ、不思議なお話ばかりでしたが、なんだか郷愁を誘われるようなというか、幼い頃身の回りの世界を知ろうともがいていた自分自身への愛しさなつかしさなどを感じ、なんだか心が温まる作品でした。
タタンという渾名をつけた小説家のいうように、「それはほんとう?それとも嘘?」なんて野暮な質問はこの作品には無用でしょう。
**********
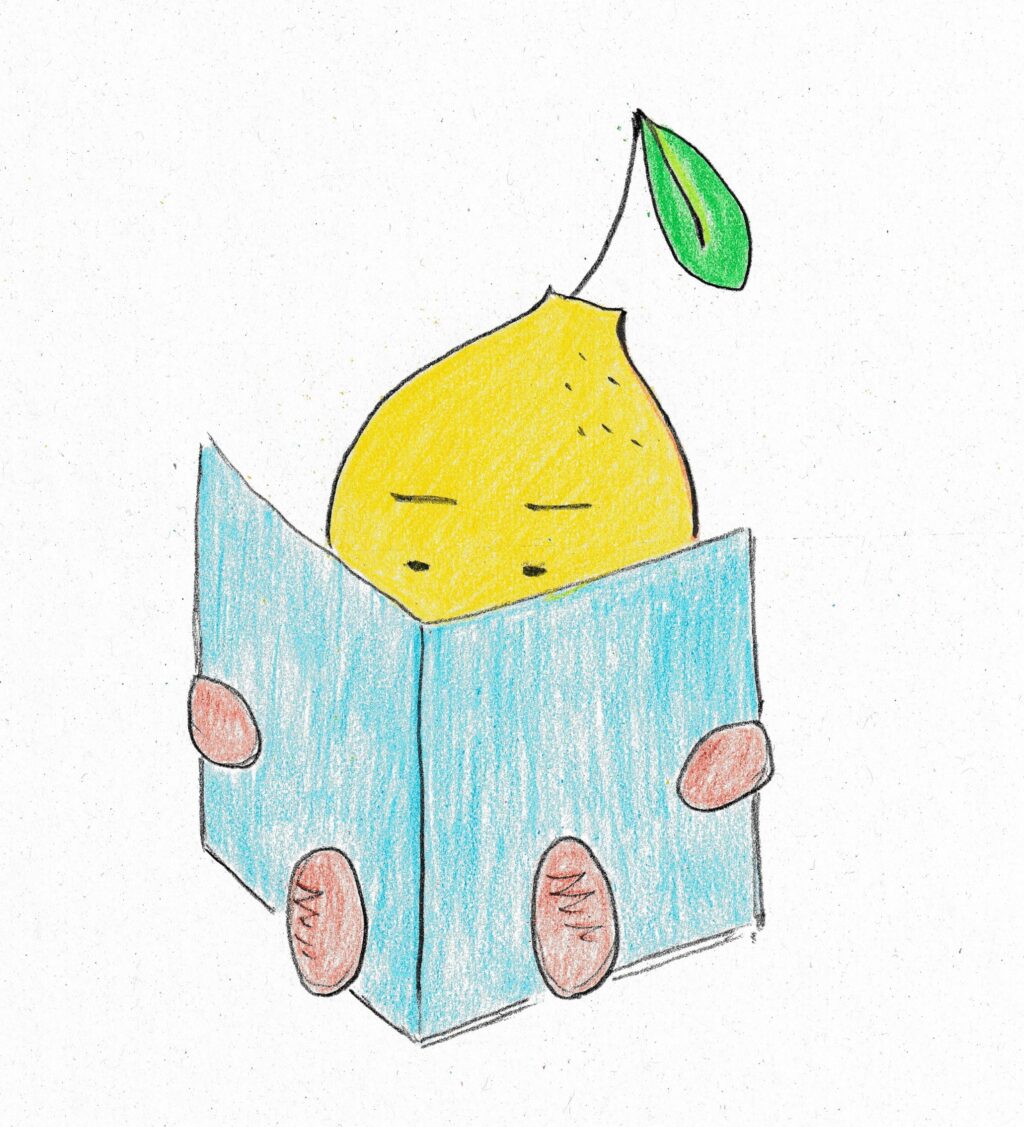
こういうちょっと不思議な物語を書ける作家さんもまた実力があるな、むむむ、と思うのですが、こういった類のお話は読み手も選びますね。フィクションやファンタジーやこういう不思議な話を好き嫌いではなく、受け入れる器のようなものを自分の中に持っていたいと思いました。
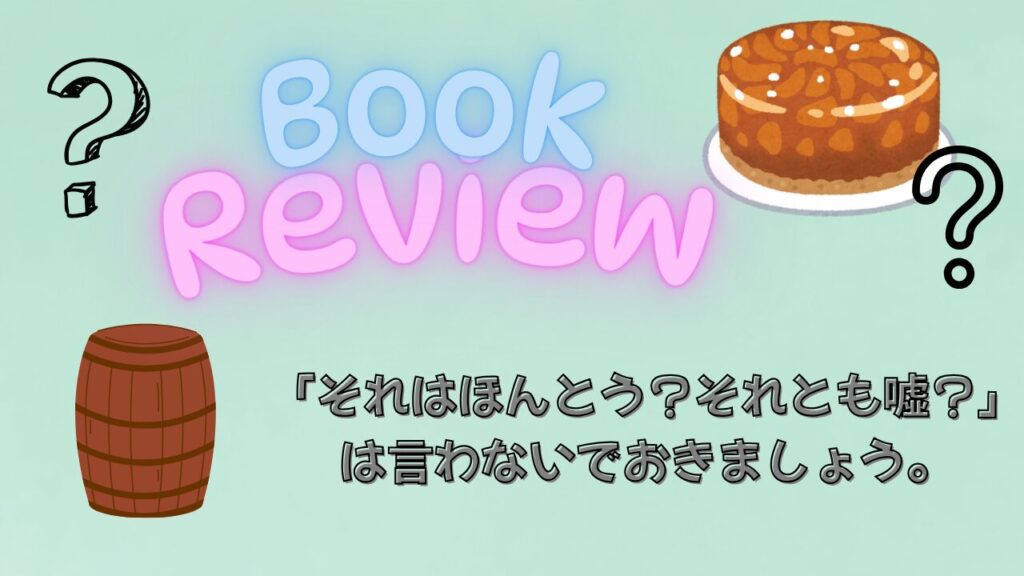


コメント