**********
先月読了した「f植物園の巣穴」とつながりがあるということで、さっそく読んでみました。
本書の主人公の曾祖父がその「f植物園の巣穴」で主人公だった豊彦さんで、豊彦さんの息子の藪彦さん(主人公からみて祖父)が、山幸彦(通常、山彦で通している)と名づけたとのこと。山彦には海幸比子(海子)という従妹がおり、ふたりはそろいもそろって「痛み」に悩まされているというところから物語が始まります。
たまたまですが、病院の待ち時間で読み始めてしまい、私自身には何の痛みもなかったものの、山彦海子のような痛みを、周囲の患者さんたちも感じているのかも、と思うと、なんともいたたまれない気持ちになりました。病院で読む本ではなかった(笑)
さて、海子の積極的な行動によって、この「痛み」はどうも、先祖の方まで遡る何かに関わっている、実家の方(佐田家の持ち家であるものの、山彦も海子も行ったことのない実家)に関わってくるのでは、という話になってきます。
正直に申しますと、全ては私の読解力のなさが原因ですが、「f植物園の巣穴」よりも理解が及びませんでした。というか、「f植物園の巣穴」の方は、現実と夢うつつが曖昧な世界で、そこまで理解しようと思わなかったというのが本当のところですが、本書はそうはいかなかった。佐田家の実家で大昔に起こった惨事、洪水の被害、活火山の山体崩壊とそれによる神社の崩壊などなど、過去に起こったことが連綿とつながり、今の山彦海子の痛みにつながっている・・・多くの出来事に頭は混乱するし、神話はなかなか頭に入ってこないし、この物語のスケールの大きさに圧倒されて・・・。
「f植物園の巣穴」は本書の中で、「f植物園の巣穴に入りて」と題した豊彦さんが書き残した超重要な書類として出てきます。これを読むことで山彦海子が先祖や実家、ひいては椿宿に対する理解を深めたようです。
「治水」・・・そういえば、豊彦さんは「治水」に対して具体的な何かをせずに、「f植物園の巣穴」は終わった気がします。それが代々引き継がれたということでしょうか。
そして、おそらく物語の本筋といえないところでひっかかってしまいました。それは、山彦さんが宙彦さんに書いた手紙の冒頭で、自分の母親から虐待とまでは言えないものの、生きるエネルギーを少しずつ削られるような育てられ方をした、と語るところです。表立った虐待でない分、質が悪いというニュアンスだったのですが、この手紙の前までに母親は登場していて、山彦さん側から母親に対して一方的に深い溝のようなものを感じていたのは充分わかっていたのですが、それでも「虐待」という言葉まで出てきたのにはびっくりしたものです。そこまでだったのか、と。ここに引っかかった理由はいくつかあって、まず、恐らく母親側はそこらへん全くの無自覚らしいので、私自身も子どもたちにとって同じような親になってはいないか、という恐れを感じたこと。母親からしたら愛情いっぱい育てたつもりの子にこのように思われているという悲劇を考えると、母親へも同情したということ。それから、表立っていない虐待(たとえば人格を否定するような言葉など)に苦しんでいる子どもたちが、表立っている虐待(身体的な暴力や食事を与えないなど)に苦しんでいる子どもたちの影に隠れてどれほどいるのだろうと想像してしまって胸がつまったこと。そして、また最初の理由「私自身がそうなっていないか」に戻って、ぐるぐると思考してしまいました。これは、山彦さんとお母さんの「質」が違いすぎたために起こった気もしますが、難しい問題だな、とすごく引っかかってしまいました。
物語の本筋に記憶を戻して、さらに正直に申しますと、同じ主題の本(「f植物園の巣穴」と本書)を続けて読んだためか、少し、著者ならではの言い回しやその世界観におなか一杯になってしまったところもありました。
ただ、やはり惹きつけられる何かがあることは否めません。梨木香歩さんが一番好きな作家さんのひとりであることに間違いはないです。
山彦の痛みに対する言葉を引用します。
「私は長い間、この痛みに苦しめられている間は、自分は何もできない、この痛みが終わった時点で、自分の本当の人生が始まり、有意義なことができるのだと思っていましたが、実は痛みに耐えている、そのときこそが、人生そのものだったと、思うようになりました。痛みとは生きる手ごたえそのもの、人生そのものに、向かい合っていたのだと。考えてみれば、これ以上に有意義な「仕事」があるのでしょうか。」
こんな言葉を紡ぐようになるには、あとどれほどの人間修行が必要だろうかとしみじみ感じました。
またいつか、何年後かに「f植物園の巣穴」と併せて再読したいです。そのころにはもうちょっと私の読解力が高まっていて、人間修業ができていますように。
**********
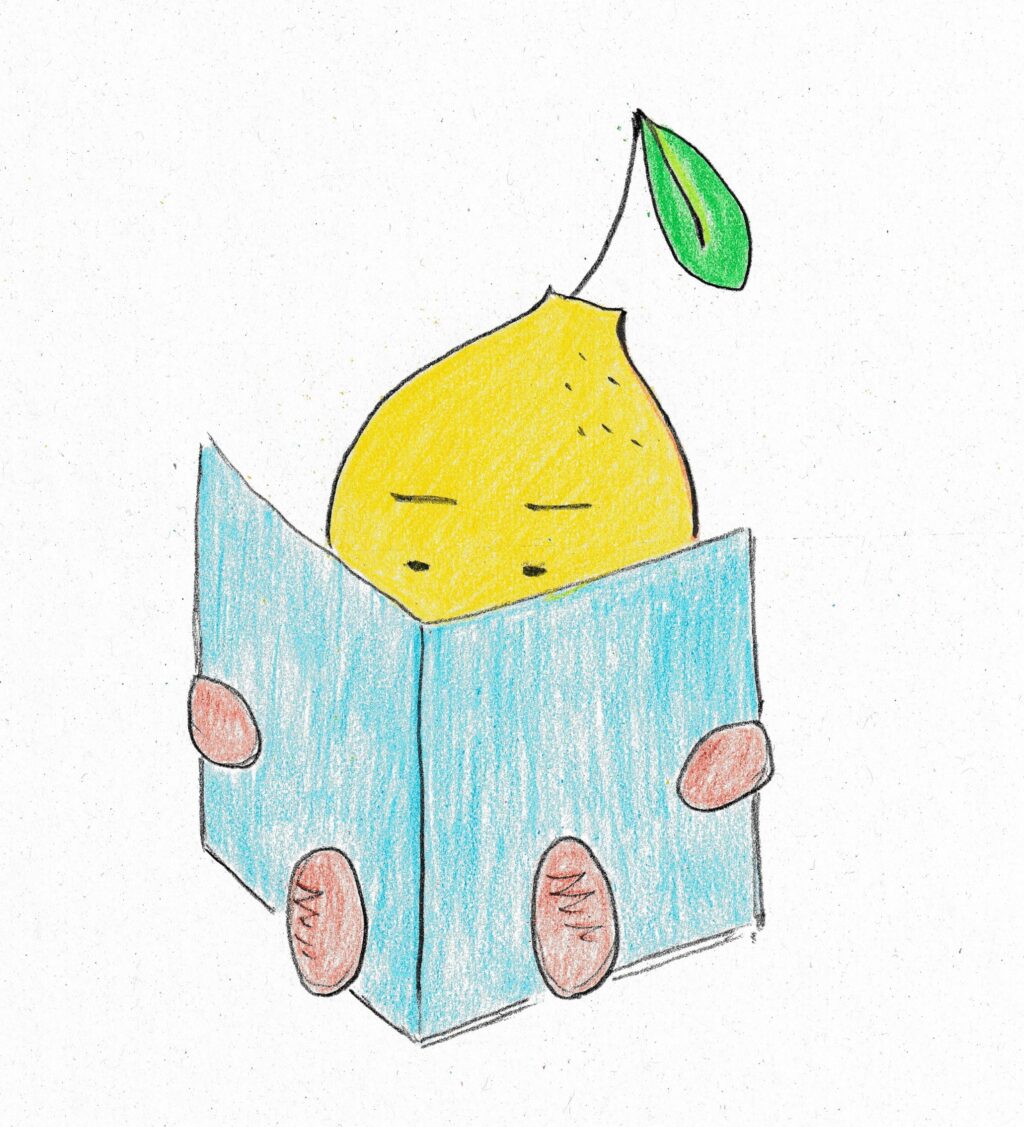
「海うそ」を読んだときに、なんて壮大な物語を作れる人なんだろうと、思ったのですが、これも先祖代々から続く壮大な物語でした。なんというか、本当にこういう脈々と続く何かがある家系ってあるんだろうな~、そういうのがいっぱいいっぱい集まってひとつの歴史になっていくのだろうな~とまとまりのない思いにふけった読後でした。
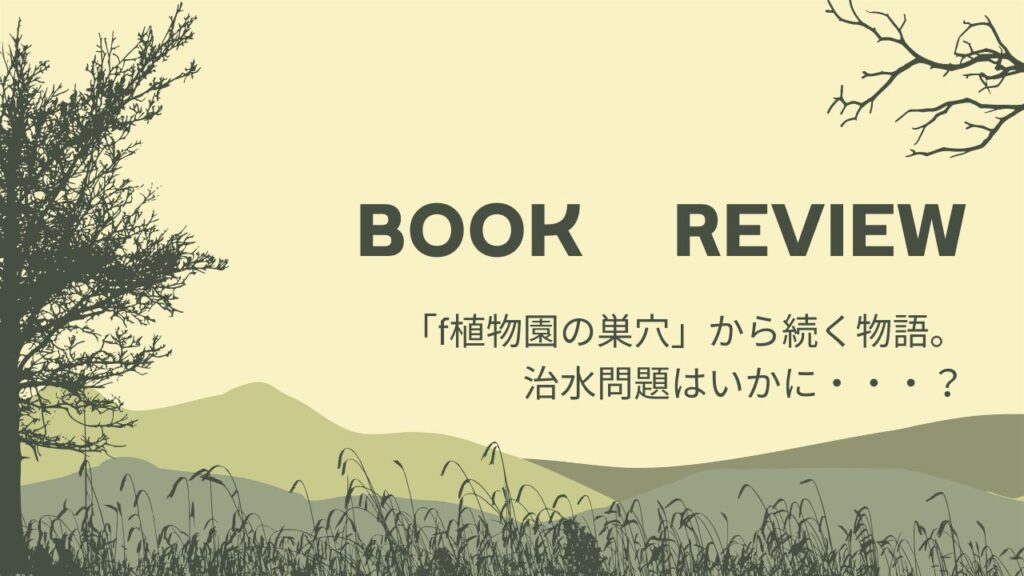


コメント